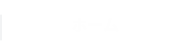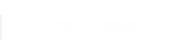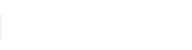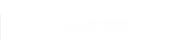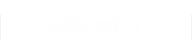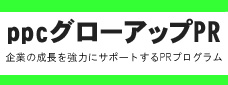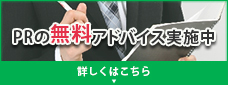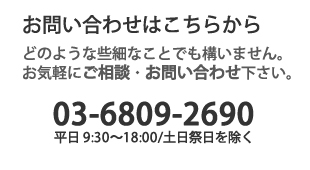農業女子のPR力
8月31日はやさいの日で、独立行政法人農畜産業振興機構主催シンポジウムに参加しました。前半のプログラムは「農業女子的野菜の魅力の伝え方 ~小さい農家の情報発信と提案方法~」で、講演者はさいたま市内で農園を運営する榎本房枝さんです。タイトルからして、日常的なビジネスのHow to話を予想していたのですが、大違い。滝に打たれたような時間でした。
さいたま市で400年続く農家に生を受けた榎本さんは、少女の頃からジェンダー差別と向き合うことになります。「跡取りは男しか要らない。女は高校までしか面倒をみない」と言われて育った彼女は、「食」で身を立てようと、当時は成績の芳しくない生徒が進むとみなされていた農業高校をあえて目指し、食品加工を学び、卒業後、料理の道に入ります。女性料理人は珍しかった時代に、またしても差別と闘う日々のなか、現場も知らずに西洋料理を語る先輩たちに疑問を抱いた彼女は、『天皇の料理番』さながらに、日本を飛び出しヨーロッパの食を探訪する放浪の旅に出発。20カ国、500都市の食を体験して1年後に帰国します。「何があっても、絶対やってやる!」と心に決めて旅立った彼女は当時まだ20代。旅の中では、思い出すと言葉に詰まるような怖い思いもあったようです。
帰国後、西洋での見聞を基盤に、那須の有名ホテルのサービススタッフとして、農家&料理人出身の経歴も生かしながら華々しい活躍をした榎本さんですが、ふとしたきっかけで、勤めていたホテルにいることができなくなり、実家に退散。このときから数ヶ月は、引きこもり状態になったと言います。ところが、引きこもってばかりはいられない事態が発生。父親逝去に続いて農園で契約していた取引がことごとく破棄され、家族共々途方に暮れる嵌めに・・・。農園再起をめざして立ち上がった彼女は、レストランへの販売に着目し独自のプチトマトを生産。レストランを回って、「試食してみてください」という活動の繰り返しが実を結び徐々に取扱店が拡大。さらには縁を生かしてシンガポールのホテルで「榎本農園フェア」を実現するまでに成功。そして・・・というお話でした
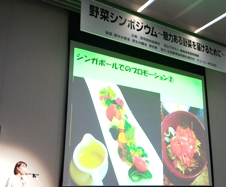
榎本さんがお話しを始めたとき、正直、「とても力の入った話し方をする方だな」と感じ、1時間以上、お話を聴き続けているのは大変かも知れない、という思いがよぎりました。ところが、お話を聴いていると、逆に、ソフトで卒のない通り一遍の語り口とは違う、榎本さんのお話の仕方に共感を覚えるようになりました。私自身、ほんの短い期間でしたが、様々なプレッシャーが押し寄せて言葉を発することができないときがありました。偶然ですが、大好きだった父が弱り、まもなく亡くなった時期でした。そんな時のことを思い出しました。
終盤、榎本さんは「夢や希望という言葉は曖昧で、あまり好きではありません・・(中略)・・『絶対やってやる』という思いしかありませんでした」というように語っていました。けれども私は、逆境や怒りを常にバネにして頑張ってきた榎本さんの姿に、日本の農業や将来への夢や希望を感じたものです。そして、農業女子プロジェクトをリードする彼女の発信力、PR力の凄さに、プレッシャーを感じてもいました。2015.9.1(穂)。
* 榎本房江さんのブログ「野菜パワーと愛をお届け! 彩の国のガーデンキッチン」)
http://ameblo.jp/fufufufuchan/